REPORT
株式会社チャウス代表取締役 宮本吾一氏/2021年度第4回 「三方良し」の未来をつくる
REPORT
株式会社チャウス代表取締役 宮本吾一氏/2021年度第4回 「三方良し」の未来をつくる

むすぶしごとLAB.は第一線で活躍する経営者や専門家をお招きし、地方での仕事の作り方や働き方のヒントを探すための実践的な学びと交流の場です。2021年度第4回目の講座では、株式会社チャウス代表取締役の宮本吾一さんにご登壇いただきました。
屋台カフェの「リアカーコーヒーUNICO」や、ハンバーガー専門店「Hamburger Cafe UNICO」など多くの事業を手がけ、2010年には那須地域のマルシェ「那須朝市」をスタート。2014年には、直売所・カフェ・ゲストハウスが合わさった複合型施設「Chus チャウス」をオープンしました。
「料理ができるわけでもお菓子作りができるわけでもない。僕は何もできないんですよ」笑顔で話す宮本さん。栃木県の那須を中心に活動する宮本さんには、那須でしかできない「ユニーク」な事業展開について伺いました。
「聞く、頼る、巻き込む」で実現させる

宮本さんは、リゾートバイトがきっかけで那須に移住。那須の街には、当時から素敵なお店が並んでいたそうです。店を経営している仲間から刺激を受け、宮本さんは2003年にリアカーをコーヒー屋台に仕立てた「リアカーコーヒーUNICO」を開業。宮本さんがカウンターに立つことでその場の繋ぎ役ができ、初対面の人同士でも会話が生まれ、コミュニティが形成されることに気がついたと言います。
その2年後に開業したハンバーガー専門店「Hamburger Cafe UNICO」は、ファストフードの代名詞であるハンバーガーをあえて地産地消のスローフードとして提供。那須和牛や高原野菜、地元のお店から仕入れたパンを使用。店舗運営は、那須でお店を営む仲間にアドバイスをもらい試行錯誤したと当時を振り返ります。
「僕はもともと料理ができるわけではないので、ハンバーガーの出来は、最初はあまり良くなかったんです。だから仲良くなった地域のシェフに聞いたり頼ったりしました。プロに教えてもらうことで、次第に美味しくなっていくんですよね」
そのとき、宮本さんは改めてコミュニティの大切さを感じたと言います。さらに、ハンバーガーショップの経営を続けるうちに、食材の生産者に興味を持ったそう。
「自分の店で出しているハンバーガーを『スローフードです』と説明していながら、自分自身が肉や野菜を作る農家さんについて知らないことに気がつきました」
そこで生まれたアイディアが、食材の生産者と繋がる場を設けるための朝市。
しかし、いざ生産者の声を聴こうとインターネットで検索して地元の生産者と連絡を取ろうとしていたときは、ほとんど断られてしまったそうです。それでも、1人の農家と知り合ったのをきっかけに、その方の友達の農家を次々と紹介してもらえたそう。
「頼りたい人と友達になっちゃえばいいわけです。そうすれば最初の友達を起点に横のつながりを紹介してもらえます。頼らなければ溺れると思うくらい必死に、たくさん頼っています。知識のある人に聞く、頼る、巻き込む。この三段活用で仲間を理想に巻き込んでいきました」
ユニークを作る

これまで宮本さんが展開してきたのは、那須でしかできないことを軸にしたビジネス。
「ユニークを作ることが地域資源を磨くことになると思っています。競合が多くいる中で一位をとるよりも、ユニークな、そこにまだ無いものを作る方が、自分で価値を決めることができます」
創業当時の「Hamburger Cafe UNICO」は苦労が多かったそう。しかし、年数を重ねるにつれて人気が出てきたとのことです。
地方は、競合が少ない商品を探しやすい環境。宮本さんは「まずは自分の事業が持つユニークな要素を見つけて創業のチャンスを探してほしい」と言います。
「始まりは誰かの真似や受け売りでも、いくつかの要素を合体させて考えついたアイデアは発案者独自のもの、『ユニーク』だと思います。『ユニーク』は誰から見ても明らかな発明や変わった人しか持てないものだと思わずにチャレンジしてほしいですね」
「ユニーク」を見つける手段の一つは、地域の人とものと歴史と文化のメモ。多面的に地域の特徴を見つけ、そこで「まだ足りていない」ものを探すことが大事なのだそうです。
「『あるもの』を数えると地方って何てつまらないんだろうって思うけれど、『ないもの』を探しはじめると、都市部よりも地方の方が探しやすいですよね。とても大事な視点が得られると思っています」
朝市を実店舗にするために誕生した「chus」は直売所とカフェ、ゲストハウスの機能を持つ複合施設。さまざまな楽しみ方がありながらも産直飲食店だと一目でわかるように店内に軽トラックを展示したこともあったそう。宮本さん自身、ユニークな特徴が見やすいように工夫しているそうです。
「三方良し」の会社を育てる
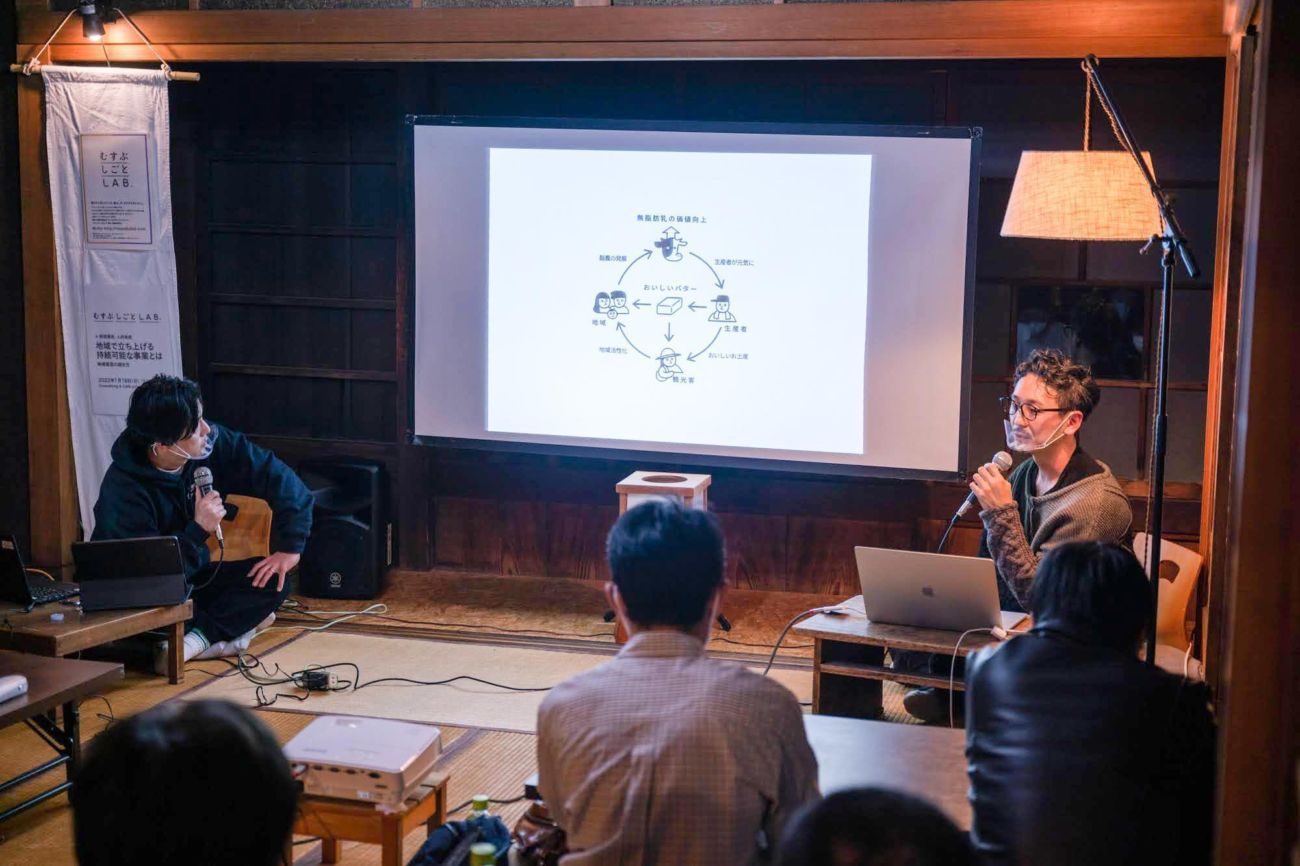
宮本さんが手がける、もう一つの独創的な事業が「バターのいとこ」。バターのいとこはバター製造時の余剰となるスキムミルクを主役に使ったお菓子。はじめは「chus」に併設した小屋で小規模に生産していましたが、徐々に人気を博し、品薄状態に。
そこで、新たにバターのいとこの工場を開設。この工場は、障害のある人が働く就労支援施設でもあります。
大学がない那須町では、進学とともに若者が都市部へ出てしまい、働き手が不足している背景があります。一方で、障害のある人が時給制で働ける場が枯渇している状況に宮本さんは注目しました。
バターのいとこの工場で働く方の多くは、精神障害を持つ人たち。長い時間働くことが苦手な人も多いと言います。そこで、勤務シフトを通常の半分の4時間で組んだり労働時間を1分単位で計算したりすることで、より働きやすい環境を整えました。
この勤務体制は、結果として子育て中の主婦にも働きやすい時間設定にもつながったと言います。
「みんなが元気になれるようにという意味で『三方良し』という言葉が好きなんです。労働環境を整えて、多くの人が働きやすくなると、労働力が上がって、生産力も上がります。そうすると、バターのいとこに関わる生産者、消費者、地域に良い循環が生まれる。ソーシャルグッドな事業は、社会だけではなく、事業をやる自分たちのためにもすごく有用な仕組みになるのだとバターのいとこの工場を通じて分かりました」
さらに2021年、宮本さんは、持続可能な街づくりに取り組む株式会社GOODNEWSを設立。那須地域の資源でもある観光と農業に福祉を掛け合わせ「観福農」の連携を産み出し、皆が幸せになれる新たな産業づくりをスタート。様々な人が関わり合うコミュニティが那須から広がろうとしています。
会社という共同体で生き抜く

講義の最後には質疑応答が行われました。
「社員とコミュニケーションをとる際に気をつけていることはありますか」という質問には、宮本さんは次のように答えました。
「できる限り一緒にまかないを食べたいと思っています。社員の皆さんとはフラットに話をしたい。社長とか社員は上下関係ではなくて役割だと思っているんです。自分はただビジョンを示して舵取りをする旗振り役だと思っています」
また、社員とのコミュニケーションのきっかけを作るために複合施設「chus」では1chus=1円として使用可能な社内通貨を導入。社内通貨で地元産の食材の購入を勧めることで、会社で取り扱う作物を知る機会にもなっているそう。
「一緒に働くスタッフに求めることは?」という質問には、「会社は共同体に過ぎないので良いことも悪いことも自分ごととして考えてほしいですね。会社という場所を使って生き抜いてほしいと思っています」と語りました。
今回の講座では、宮本さんの事例を伺いながら、宮本さんの目指す「三方良し」の地域を支える経営方法について伺うことができました。